映画レビュー:どうすればよかったか?
- Pro SciBaco
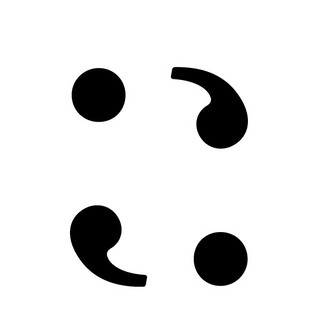
- 2024年12月19日
- 読了時間: 3分
いつもChat Potで触れている科学技術コミュニケーションと映画ですが、今回はニューズレターの記事として触れていきます。
紹介するのは、この冬話題のドキュメンタリー、「どうすればよかったか?」です。
舞台は札幌、監督の藤野智明さんは北海道大学出身であり、札幌にゆかりの深い作品です。現在、札幌ではシアターキノで公開中で、全国の映画館でも公開されています。
本作は家族の袋小路を20年にわたり追ったドキュメンタリーです。医学系の研究者である両親、そして医学部に通う優秀な姉。ある日姉が精神疾患の症状を発症します。しかし両親はその症状を病気とは認めません。症状がどんどん悪化する姉、それを受け流す両親、袋小路に陥った家族に対し、弟の藤野監督は「どうすればいいのか」という葛藤から、ビデオを回し始めます。
最初はドキュメンタリーとしての映像ではなく、監督が両親と冷静に向き合うための手段としてビデオは回されていました。やがて両親は姉を外に出さないように玄関に鍵をかけ、母も姉と共に引きこもっていきます。その日々は20年にも及びました。
さて、両親は研究者であり、医学にも通じています。しかし、こと姉の症状のこととなるとかたくなに治療を拒んでいきます。サイエンスコミュニケーションでは、科学リテラシーを育むことも、活動の一つとされています。科学リテラシーとは科学的情報を収集し、科学者のように客観的に分析し、活用する能力です。ただ、このような客観的な判断能力は、「客観的になれる状況の下では」という条件が付くことが、このドキュメンタリーは見せつけていきます。
もし姉が他人だったら、もし姉が両親とそりの合わない「かわいくない」子だったら、もし両親が精神疾患を普通の病気だと捉えていたら、色々な原因でどんな人でも客観的にいられない状況に陥ります。
早く病院に連れて行けばいいのに、藤野監督が両親を説得する場面では、私も強くそう思いました。ただ、それは私が今他人の家族を見ているから、映像越しの状況だから、という安全圏にいるから感じることなのかもしれません。
両親の選択は失敗でした。映画後半に流れる回復していく姉の様子からは、彼女の症状が両親が考えるような社会的「ビョーキ」ではなく、身体的「病気」だったことが痛感させられます。
ただ果たして「どうすればよかったか?」。愛する家族だからこそ、客観的にいられなかった両親をどう説得できたのか。サイエンスコミュニケーションに従事する身としても、今回の映画の突き付けてくる問いに簡単に答えが出せません。
映画情報


![【サイエンスライティング】人の人生に深く関わる作業療法─臨床と研究の往還から見えてきたもの/髙島理沙さん(保健科学研究院 講師)[FIKA No.16]](https://static.wixstatic.com/media/e45d73_723fd66ccb094c0f9b5567f6ed733290~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_735,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/e45d73_723fd66ccb094c0f9b5567f6ed733290~mv2.jpg)
