万博に見るサイエンスコミュニケーション
- Pro SciBaco
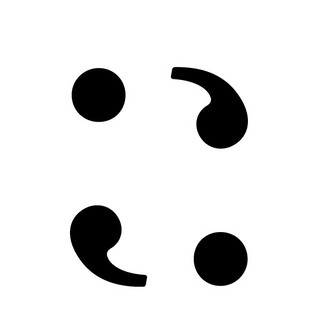
- 2025年11月6日
- 読了時間: 4分
更新日:2025年11月9日
盛況に終わった大阪・関西万博2025。今回のテーマはいのち輝く未来社会のデザインでした。そのテーマをもう少し深くひも解くと、未来のためにどのように社会全体で考え、対話的に考えていくかというサイエンスコミュニケーションのコンセプトにも通じる思いがあります。
今回は、サイエンスコミュニケーションの視点から万博のパビリオンを紹介していきます。

より対話的で、持続可能な開発を目指す大阪・関西万博
元々、先進国の産業博覧会的な意味が多かった万国博覧会が、今のようによりコンセプチュアルな内容になった経緯に、1988年に国際博覧会条約が改正された時に設けられた登録博覧会というカテゴリーがあります。登録博覧会は5年に一度、6ヶ月間開催される、参加国が自国のパビリオンを建設できる大規模な国際博覧会と定義されています。この制度が生まれてから日本で初めて開催されたのが2005年の愛・地球博です。それ以来20年ぶりの登録博覧会ということになります。
近年の万博では、発展だけではなく、持続可能性や対話的という観点も含まれるようになっています。そこにはサイエンスコミュニケーションの視点も含まれています。
対話する未来
今回の関西万博では、主に海外のパビリオン、企業パビリオン、そしてプロデューサーを招いて今回のコンセプトに沿った内容を展示するシグネチャーパビリオンの3つのカテゴリーのパビリオンに分かれます。
シグネチャーパビリオンの中でも、対話をテーマにしたものが映画監督の河瀨直美さんがプロデュースした「Dialogue Theater いのちのあかし」です。
初めて出会う二人が対話する様子を見て、対話とは何かを考えていくというのがDialogue Theaterの体験です。知らない相手と対話を探り続けることでなにが生まれるのか、サイエンスコミュニケーションにも通じる観点です。

派手な仕掛けも、最先端のテクノロジーも使われていませんが、対話を通してもがきながら進んでいくというしかけが、もしかしたら一番今日的な課題解決の手法なのかもしれません。
それは企業館の姿勢にもありました。農業用トラックなどを開発する株式会社クボタは、農業をテーマに企業ブースを出展。その中の一つに私が育てる未来の種というコーナーがありました。ここでは農業にかかわる人々の活動を紹介し、来場者がその種を一つだけ選んで持ち帰ります。
ただしここで一つの工夫が。この種のコーナーにはじっくり選ぶ時間を設けるために、1組ずつ入るという入場制限が設けられています。多数の人が訪れる万博で、入場制限を設けることは勇気がいったと思いますが、考える時間が流れ作業にならないようにという思いが伝わります。

また海外パビリオンでも対話的な展示が印象的です。ウクライナの展示では、売れないものは何?というテーマで、どんな状況でも売れないもの、そして戦争の中での人々の暮らしが紹介されています。

未来感の更新
また、持続可能性も今回の万博のコンセプト。日本館は開催国として責任をもって出したパビリオンですが、そのテーマは循環。
今回の万博から出た生ごみはすべて日本館でリサイクルされ、きれいな水として生まれ変わります。また日本館の建物は間伐材から作られたCLT(直交集成板)で作られており、万博終了後はその板はリサイクルされるそうです。

5年後に登録博覧会が開催されるサウジアラビア館でも持続可能性は大きなテーマです。砂漠のイメージがあるサウジアラビアですが、実は海にも面しています。ただし海もサンゴ礁が減少するなど深刻な環境課題を抱えています。サンゴ礁の種となる人工サンゴを作り、サンゴ礁を増やす取り組みが紹介されていました。

またシグネチャーパビリオンのEarth Martは日本の伝統食材から持続可能な食のあり方に迫ります。
日本の伝統食材を未来的な観点で見てみると、新しいパッケージ、レシピとともに、伝統料理を未来につなげる視点が紹介されています。

「これからの進歩とは、私たちが立ち止まり、未来感を更新させること」と思わせる取り組みが多々ありました。
当初は批判的な意見も多かった大阪・関西万博2025。しかし、中身はこれからの未来につながる今現在の最先端の思考が実験的に展示されていました。自分たちはこれからどのように生きていきたいだろう、全世界的に一歩立ち止まり、対話的に考えてみる、そんな貴重なきっかけが万博という取り組みなのかもしれません。


![【サイエンスライティング】人の人生に深く関わる作業療法─臨床と研究の往還から見えてきたもの/髙島理沙さん(保健科学研究院 講師)[FIKA No.16]](https://static.wixstatic.com/media/e45d73_723fd66ccb094c0f9b5567f6ed733290~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_735,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/e45d73_723fd66ccb094c0f9b5567f6ed733290~mv2.jpg)
