top of page
検索


研究評価に関するサンフランシスコ宣言とライデン宣言とは
あけましておめでとうございます。 2026年から第7期科学技術・イノベーション基本計画が始まる予定で、科学技術政策も新たなフェーズに入ります。また今年度は長年削減されてきた 科学研究費・運営費交付金も増額され、科学技術への支援が強化される見通しです。 その背景に日本の研究力が低下しているという議論があります。ただ研究力とはそもそもどういうものなのでしょうか? 研究力が下がっている議論の背景には? 研究力の低下でよく使われる指標に、 被 引用数の高い論文の順位というものがあります。論文の 被 引用数が高ければ高いほど注目されているという考えのもの、その注目論文がどの程度の順位かというものが指標になります。 2021年から2023年の日本の位置は、論文数は世界5位ですが、 被 引用数の高い論文の数が13位と低迷しているということです。確かに他の国と比較しても論文数と 被 引用数のランキングが異なるのは日本特有の問題のようです1)。 また基礎的な研究力の指標である論文の指標だけでなく、研究開発効率、つまり産業レベルでの研究開発の有効性を調査したところ、
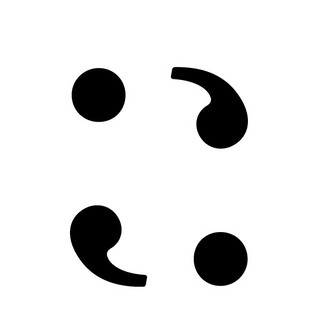
Pro SciBaco
4 日前読了時間: 14分
![【サイエンスライティング】人の人生に深く関わる作業療法─臨床と研究の往還から見えてきたもの/髙島理沙さん(保健科学研究院 講師)[FIKA No.16]](https://static.wixstatic.com/media/e45d73_723fd66ccb094c0f9b5567f6ed733290~mv2.jpg/v1/fill/w_333,h_250,fp_0.50_0.50,q_30,blur_30,enc_avif,quality_auto/e45d73_723fd66ccb094c0f9b5567f6ed733290~mv2.webp)
![【サイエンスライティング】人の人生に深く関わる作業療法─臨床と研究の往還から見えてきたもの/髙島理沙さん(保健科学研究院 講師)[FIKA No.16]](https://static.wixstatic.com/media/e45d73_723fd66ccb094c0f9b5567f6ed733290~mv2.jpg/v1/fill/w_454,h_341,fp_0.50_0.50,q_90,enc_avif,quality_auto/e45d73_723fd66ccb094c0f9b5567f6ed733290~mv2.webp)
【サイエンスライティング】人の人生に深く関わる作業療法─臨床と研究の往還から見えてきたもの/髙島理沙さん(保健科学研究院 講師)[FIKA No.16]
シリーズ16回目となる今回は保健科学研究院の髙島理沙さん。 髙島さんは、作業療法士として臨床現場に携わった後、研究の道に進みました。患者一人ひとりの人生に寄り添いながら「作業」を通じて生活を支える作業療法の魅力を、臨床と研究を行き来しながら探究しています。博士課程では質的研究が十分に理解されず、大きな挫折を経験しましたが、「質的研究の意義を社会に伝えたい」という強い思いを原動力として、現在は教育や研究を通じて、次世代に作業療法の可能性と質的研究の価値を広めています。 【森沙耶】 本文はいいね!Hokudaiをご覧ください。
mori saya
2025年12月25日読了時間: 1分


令和7年度北海道コーディネータ・ネットワーク・フォーラムに弊社代表が登壇します。
「つなぐ」をテーマに令和7年度北海道コーディネータ・ネットワーク・フォーラムが2026年1月27日14:00~16:40に赤レンガ庁舎(北海道庁旧本庁舎)にて開催されます。 「つなぐ」コーディネーター 地域がより活性化するには、組織同士、組織と個人、そして個人と個人の「つながり」が重要です。そこで大きな役割を果たしているのが、コーディネーターです。 しかし、コーディネートという役割は、特定の人に依存してしまいがち(属人化しやすい)な側面もあります。本フォーラムでは、 サイバコ の事業で見えてきたコーディネートのポイントをご紹介します。 そして、「つなぐ」ことで地域の活動が発展するにはどのような支援が必要かについて、皆さんと一緒に話し合います。 当日はオンライン配信も行いますので、ご興味のある方は、ぜひご参加ください。

Mineyo Iwase
2025年12月18日読了時間: 1分


大学の社会的インパクトをどう表現するか?~室蘭工業大学「社会的インパクト表現プロジェクト」の紹介~
サイバコでは、室蘭工業大学MONOづくりみらい共創機構パブリックリレーションズ(PR)オフィス主催の「社会的インパクト表現プロジェクト」をお手伝いしています。 室蘭工業大学PRオフィスは、「室蘭工業大学の知られざる価値を地域に届ける」ことを目標に活動しています。その活動の一つとして「社会的インパクト表現プロジェクト」を実施しています。これは、室蘭工業大学の構成員である教職員の活動が、社会や環境にもたらした変化や効果である 「社会的インパクト」を可視化し、学内外に広く知ってもらう活動 です。 社会的インパクト表現プロジェクトとは 室蘭工業大学の価値ある研究成果や取り組みを、社会的インパクトにつながる形で教職員自身が表現できるようになることを目的に、始まりました。 サイバコがお手伝いしていることは2つ。まずは 「ニュースレター」の制作 です。 大学内で本プロジェクトの認知や理解を促進するため、室蘭工業大学が社会的インパクト表現プロジェクトをどのように進めようとしているのか、研究者の実践事例紹介を盛り込みながらニュースレターを制作、定期的に発行していま

Junko Wada
2025年12月11日読了時間: 3分


ノーベル賞におけるサイエンスコミュニケーション
12月はノーベル賞の授賞式があります。2025年度は日本人研究者が2名受賞するなど大きな話題もありました。今回はノーベル賞を通してサイエンスコミュニケーションを考えていきます。 ノーベル賞を科学する 科学系のノーベル賞の受賞者を研究することで、どのような研究や研究キャリアが世界的な研究成果を生み出すのかを考察することができます。アメリカの社会学者、ハリエット・ズッカーマンはノーベル賞受賞者を対象に詳細なインタビューやキャリア分析を行い、科学界におけるエリートの構造や業績評価の仕組みを研究しました。彼女の研究成果は「科学エリート:ノーベル賞受賞者の社会学的考察」という書籍として1977年に発表され、日本でも1980年に翻訳本が出版されました。 彼女の研究で発見されたことのひとつに「マタイ効果」があります。マタイ効果は名声によって科学的成果の評価が上がる現象を指します。すでに名声のある研究者は、無名の科学者と同じような業績を上げても、より多くの称賛や信用を得やすく、また著名な研究者と共同研究を行うことでも評価が上がりやすい傾向があります。そのため
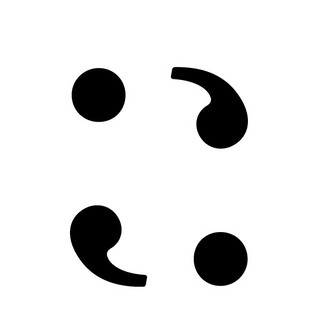
Pro SciBaco
2025年12月5日読了時間: 6分


「伝える」から「伝わる」仕組みへ
教育工学が解き明かすサイエンスコミュニケーションの「How」 サイエンスコミュニケーションは、専門家が一方的に知識を伝える時代から、市民との双方向的な対話を目指す時代へと変化しました。そこで求められるのが、「伝える」技術から「伝わる」ための設計へのシフトです。対象者に合わせた最適な「介入(デザイン)」を行う教育工学の視点を取り入れることで、私たちのコミュニケーションはどう変わるのか。その可能性を探ります。 私たちが教育工学を学ぶ理由 私たちがサイエンスコミュニケーションのサービスを提供する際、その理論的背景にしている分野に「教育工学(Educational Technology)」があります。 教育工学は、教育現場の改善に役立つ効果的な技術や工夫を開発・設計し、その効果を評価することを目的としています。その基礎には、教育学、教育哲学、教育心理学、学習科学、経済学、人類学、統計学、情報科学など、極めて多様な分野が含まれます。また研究フィールドも、幼児教育から生涯教育、医学教育、キャリア教育、企業内教育など、人が学ぶあらゆる実践の場に広がってい

Mineyo Iwase
2025年11月27日読了時間: 4分


サイエンスライティングとは? ~『サイエンスコミュニケーションの道具箱』より~
今日は、サイバコの得意分野のひとつである「サイエンスライティング」について、CoSTEP20周年を記念して発行された『サイエンスコミュニケーションの道具箱』を引用しながら説明したいと思います。 サイエンスライティングとは? サイエンスライティングとは、科学的な内容を文章によって伝える技術です。専門家の間で共有される論文や報告書とは異なり、科学の知見や発見を専門外の人たちにも理解できる形で表現できることを目指します。 (中略) すぐれたサイエンスライティングは、単に科学的事実を伝えるだけではなく、その背景や意義、社会との関わりを伝え、読者の好奇心を刺激します。難解な概念を身近なたとえで説明したり、専門用語を噛み砕いたりすることで、科学の世界と日常の架け橋となります。 (『サイエンスコミュニケーションの道具箱』P12) サイバコに多く相談寄せられることのひとつに、「専門分野のことを専門分野外の方にわかってほしい」というものがあります。わかってもらうためには誰に・どのような方法で伝えるのがよいか、お客様と対話を重ねて解決方法を探ります。その際、より多く

Junko Wada
2025年11月20日読了時間: 3分


万博に見るサイエンスコミュニケーション
盛況に終わった大阪・関西万博2025。今回のテーマは いのち輝く未来社会のデザインでした。そのテーマをもう少し深くひも解くと、未来のためにどのように社会全体で考え、対話的に考えていくかというサイエンスコミュニケーションのコンセプトにも通じる思いがあります。 今回は、サイエンスコミュニケーションの視点から万博のパビリオンを紹介していきます。 より対話的で、持続可能な開発を目指す大阪・関西万博 元々、先進国の産業博覧会的な意味が多かった万国博覧会が、今のようによりコンセプチュアルな内容になった経緯に、1988年に国際博覧会条約が改正された時に設けられた登録博覧会というカテゴリーがあります。登録博覧会は5年に一度、6ヶ月間開催される、参加国が自国のパビリオンを建設できる大規模な国際博覧会と定義されています。この制度が生まれてから日本で初めて開催されたのが2005年の愛・地球博です。それ以来20年ぶりの登録博覧会ということになります。 近年の万博では、発展だけではなく、持続可能性や対話的という観点も含まれるようになっています。そこにはサイエンスコミュニケ
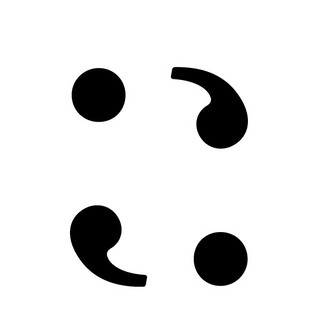
Pro SciBaco
2025年11月6日読了時間: 4分


「クセ」は脳の知恵?
なぜ一度勝つと次も勝ちやすく、負けるとまた負けてしまうのでしょうか。 実は、「勝者敗者効果」と呼ばれるこの現象は、魚から人間にまで共通して見られる行動パターンです。最近、そのメカニズムを明らかにした論文が発表されました。自分のクセを振り返る良い機会になったので、紹介します。 「勝ったあと」と「負けたあと」に起きる不思議な変化 「勝者敗者効果」とは、直近の勝敗経験が次の勝負の成績に大きく影響を及ぼす現象です。勝利した経験を持つ個体は次に勝ちやすく(勝者効果)、負けた経験を持つ個体は次に負けやすくなります(敗者効果)。この効果は、魚類(トゲウオ)、爬虫類(アメリカマムシ)、哺乳類、鳥類、甲殻類、昆虫など、幅広い動物種で確認されています。特筆すべきは、実力(体格やサイズ)にかかわらず、直前の勝敗がその後の勝率を劇的に変える点です。 また、勝敗がその生物の社会的階層(ヒエラルキー)に影響を及ぼすことも知られています。負け続けるということは、単に一時的な劣勢を意味するだけでなく、群れの中での立場や行動パターンをも変化させる可能性があります。マウス同士を

Mineyo Iwase
2025年10月16日読了時間: 4分


科学の宣言とCoSTEP宣言
科学とは何かを社会的に定義したブタペスト宣言、そしてその20年後に策定されたポストブタペスト宣言をご存じですか?SciBacoは北大CoSTEPから派生したスタートアップ企業ですが、そのCoSTEPが二つの宣言を軸にサイエンスコミュニケーションの宣言、CoSTEP宣言を先ほ...
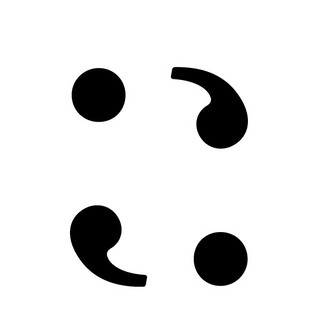
Pro SciBaco
2025年9月26日読了時間: 4分


女性研究者のフロントランナーを紹介するインタビューシリーズ「LILAS」第五段は医学研究科の玉腰暁子さん
フロントランナーとして活躍している女性リーダー(Leader)を紹介する女性研究者インタビューシリーズLILAS。リラはフランス語で札幌の花としても知られるライラック(Lilac)を意味します。 インタビューの内容から着想を得た植物のアレンジメントとともに、植物の持つ力強さ...
mori saya
2025年9月11日読了時間: 1分


社会的インパクト評価は「羅針盤」
社会課題解決の取り組みは成果が表れるまでに時間を要します。その進捗を確かめ、未来の意思決定に活かす仕組みが「社会的インパクト評価」です。多様な関係者が評価的マインドを持ち、問い直しと見直しを重ねること。その柔軟さこそが未来を共創する力となるのではないかと考えています。...

Mineyo Iwase
2025年9月4日読了時間: 5分


サイバコのホームページをリニューアルしました
本日、サイバコのホームページをリニューアルしました。 https://www.scibaco.biz/ 内容のわかりやすさや、デザインから視覚的に伝えられる部分にこだわったことはもちろんですが、 私たちが実現したいことやその道筋を改めてみんなで考え、整理し、表現しました。...

Junko Wada
2025年8月29日読了時間: 2分


モード1の科学とモード2の科学
科学のモード論をご存じですか?科学技術の生産スタイルをモード(様式)として整理したものです。 モード論には主に旧来の科学と呼ばれる活動と、20世紀から21世紀にかけて生まれた新しい科学の潮流の違いを分析するために使われます。...
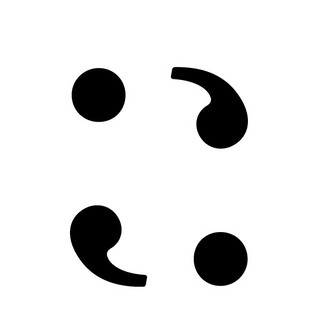
Pro SciBaco
2025年8月21日読了時間: 5分


サイエンスカフェの準備、進行中です
今週のサイバコは、明日の小学生向けサイエンスカフェ&ワークショップの開催に向けた準備の総仕上げということで、ラストスパートの1週間でした。 今回のサイエンスカフェでは北広島市のFビレッジにある、食と農の学習施設であるクボタ...
mori saya
2025年8月8日読了時間: 2分


BBQのごちそうは北海道産牛肉・ホタテ、未来へのエネルギー
札幌では雪解けが進む5月半ば頃から、野外でのバーベキューのシーズンが始まりますが、6月くらいからは、職場でも駐車場やちょっとした広場でお肉の焼ける香ばしい匂いと楽しそうな声が漂ってくるようになります。 「サイバコ」からの帰り道、にぎやかな声に誘われて目を向けると、バーベキュ...

Mineyo Iwase
2025年7月31日読了時間: 2分
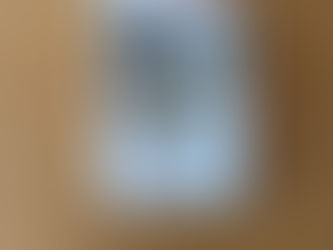
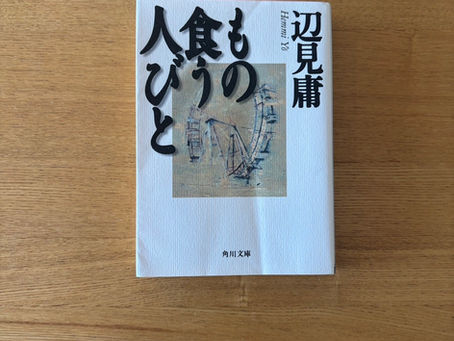
KPIだけで「目指した変革」は計れるか?
正直に白状すると、私は小学生のころ、授業を全くまじめに聞いていない子どもでした。興味がもてない授業はもっぱら絵を描いたり物語を作ったり。それも集中できないときは、いまこの瞬間、私の行ったことのない外国ではどんなことが起こっているのだろうと想像していました。例えば誰かがくしゃ...

Junko Wada
2025年7月25日読了時間: 2分


女性研究者のフロントランナーを紹介するインタビューシリーズ「LILAS」第四段は北方生物圏フィールド科学センター 室蘭臨海実験所の長里千香子さん
フロントランナーとして活躍している女性リーダー(Leader)を紹介する女性研究者インタビューシリーズLILAS。リラはフランス語で札幌の花としても知られるライラック(Lilac)を意味します。 インタビューの内容から着想を得た植物のアレンジメントとともに、植物の持つ力強さ...
mori saya
2025年7月10日読了時間: 1分


【サイエンスコミュニケーションと法#7】外来種を取り締まる法律は?
サイエンスコミュニケーションに関係する最近施行された法律について解説していく「サイエンスコミュニケーションと法」という連載、第7弾は最近、超危険な植物?が札幌に見つかったとの報道があり、話題になっている外来種です。
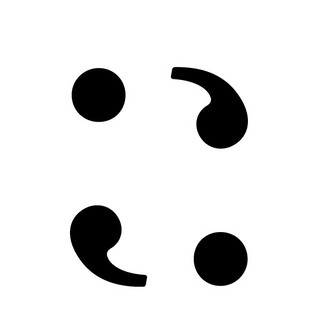
Pro SciBaco
2025年7月3日読了時間: 5分


サイバコがやっているのは「サイエンスコミュニケーション」?
サイバコに参画して、早くも3か月が経とうとしています。あっという間でしたが、それでも最初に作った50枚の名刺は早々に無くなり、多くの方にサイバコについて説明する機会をいただきました。 CoSTEP (北海道大学の科学技術コミュニケーター養成講座)受講者だった私からすると、「...

Junko Wada
2025年6月27日読了時間: 2分
bottom of page
