【サイエンスコミュニケーションと法#7】外来種を取り締まる法律は?
- Pro SciBaco
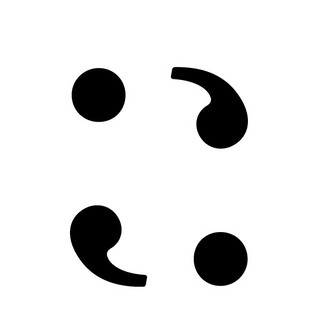
- 2025年4月24日
- 読了時間: 5分
更新日:2025年7月3日
サイエンスコミュニケーションに関係する最近施行された法律について解説していく「サイエンスコミュニケーションと法」という連載、第7弾は最近、超危険な植物?が札幌に見つかったとの報道があり、話題になっている外来種です。

世界一危険な植物?
先日、北大構内でバイカルハナウドとみられる植物が発見されました。バイカルハナウドは英名でジャイアント・ホグウィードと呼ばれ、北海道の在来種、オオハナウドにもよく似ています。
ただ、バイカルハナウドは光毒性の物質を含み、人が触ると水泡ができてしまうという危険性があります。ウドとして食用にもなるオオハナウドとは見た目は似てても、危険性はまるで違います。
外来種を予防するには3つの原則があります。
入れない 悪影響をもたらす恐れのある外来種を、地域に持ち込んではいけません
捨てない もし自分で飼育、栽培している場合、絶対に捨ててはいけません。
拡げない 野生で繁殖してしまっている外来種は、それ以上拡げない努力が必要です。
北大構内で発見されたバイカルハナウドと思しき植物はその日のうちに隔離され、現在は除草されています。ただし、最近新たに札幌の別の地域でもバイカルハナウドと疑われる植物が見つかっており、すでに市内では繁殖しているのか、と懸念されています。
外来種とは?
バイカルハナウドはどこからから持ち込まれた植物、つまり外来種だと言われています。人工的に持ち込まれた外来種は、環境や私たちの生活に深刻な影響をもたらすことがあります。もちろん環境で駆逐される外来種も会いますが、環境に適合し、在来種や自然環境に大きな脅威をもたらす外来種を「侵略的外来種」と言います。日本ではこの侵略的外来種対策のために、外来生物法という法律があります。
2005年に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)」が施行され、「特定外来生物」と呼ばれる環境や人体に影響をもたらす外来種は原則、飼育、栽培、保管、運搬、輸入、野外への放出などが禁止されています。例えば、農業被害をもたらすアライグマ、在来種に影響が懸念されているブルーギルなどがそれにあたります。外来種の中には、定着している外来種と、定着はしていないが懸念されている外来種があります。
特定外来生物を許可なく放したり、飼育したりすると、個人は懲役3年以下または300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金が科せられます。とても重い罪ですね。
また毒を持つヒアリはまん延したら重大な影響をもたらすとされており、要緊急対処特定外来生物に指定されています。
外来種は通常海外から持ち込まれる生物ですが、北海道のように従来本州とは違う生態系が栄えている地域は、国内の種も「国内外来種」として環境に深刻な影響をもたらす場合があります。例えば北海道にはもともとカブトムシがいませんでしたが、昆虫ブームによって持ち込まれ、いま在来種であるクワガタを脅かしています。
外来種の末路
外来種を駆逐するのはたやすいことではありません。奄美大島のマングースは20年ほどかけて根絶に成功しました。ただ、この駆逐には非常に長い時間をかけて、地域の人々の熱意で駆除が進んだ結果です。一度繁栄した外来種を駆逐するのは簡単なことではありません。
ただ自然に減少した事例としてセイタカアワダチソウの例があげられます。かつて日本の空き地に反映していたセイタカアワダチソウですが、近年は減少傾向にあり、その理由として他の植物に対して出していた成長阻害物質が自分の仲間の抑制に使われたのではないか?天敵のウドンコ病などが入ってきたことによる影響ではないかと様々な推察がされています。ともかく、猛き者もつひにはほろびぬ、ひとへに風の前の塵に同じ、とは外来種にも当てはまるかもしれません。生態系事態を破壊してしまった結果は最後は外来種にも影響を及ぼします。
サイエンスコミュニケーションの難しさ
外来種であっても、命ある生物であることは変わりありません。その駆逐については、環境のためとはいえ、心が痛むものです。サイエンスコミュニケーションにおいても外来種の命を粗末に扱っていいわけではありません。
またかわいい見た目の外来種はなおさら人々の保護欲を高めます。例えばネコ、実は多くの生き物を絶滅に追いやった侵略的外来種の典型的な存在です。ネコの駆除を進めようとするとするには、多くの人の感情的葛藤を乗り越える必要があります。
ネコは侵略的外来種にも選ばれていますが、現在、その歴史の長さからも通常の駆除の対象になっていません。しかし被害が深刻な地域は条例を作り、飼い猫にマイクロチップを埋め込み登録管理する場合もあります。北海道の天売島、東京都の小笠原村、沖縄の竹富町などが有名です。特に北海道の天売島は稀少な海鳥を守るため、野良猫を捕獲して、島外搬出や飼い主を見つけるなどの取り組みを行い、この問題を解決しようとしています。
持ち込んだ人間の業を反省するとともに、環境全体のバランスのための駆除を訴え、外来種を管理させることができるのか、サイエンスコミュニケーションにおいては法律では乗り越えられない壁を越えていきます。


![【サイエンスライティング】人の人生に深く関わる作業療法─臨床と研究の往還から見えてきたもの/髙島理沙さん(保健科学研究院 講師)[FIKA No.16]](https://static.wixstatic.com/media/e45d73_723fd66ccb094c0f9b5567f6ed733290~mv2.jpg/v1/fill/w_980,h_735,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/e45d73_723fd66ccb094c0f9b5567f6ed733290~mv2.jpg)
